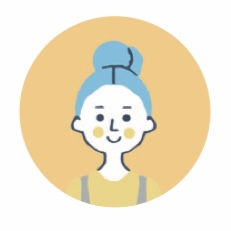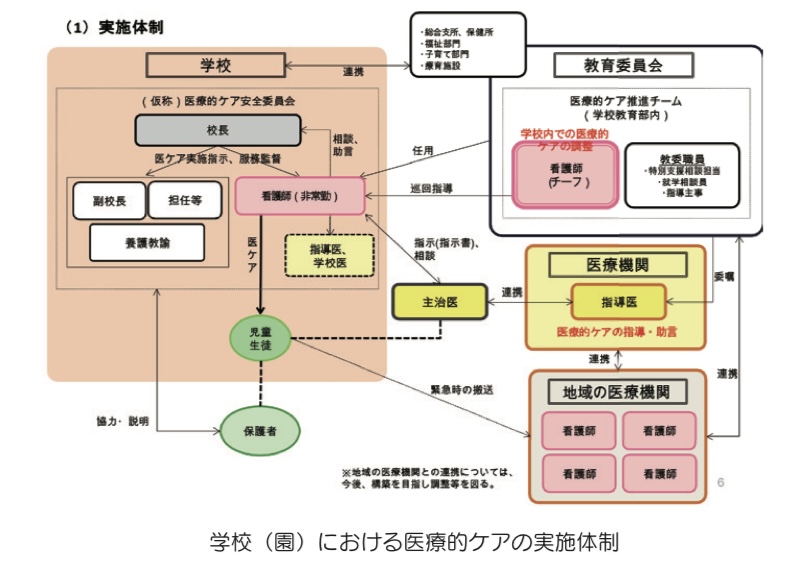事例紹介(練馬区)(5)『医療的ケア児就学事例集2022』
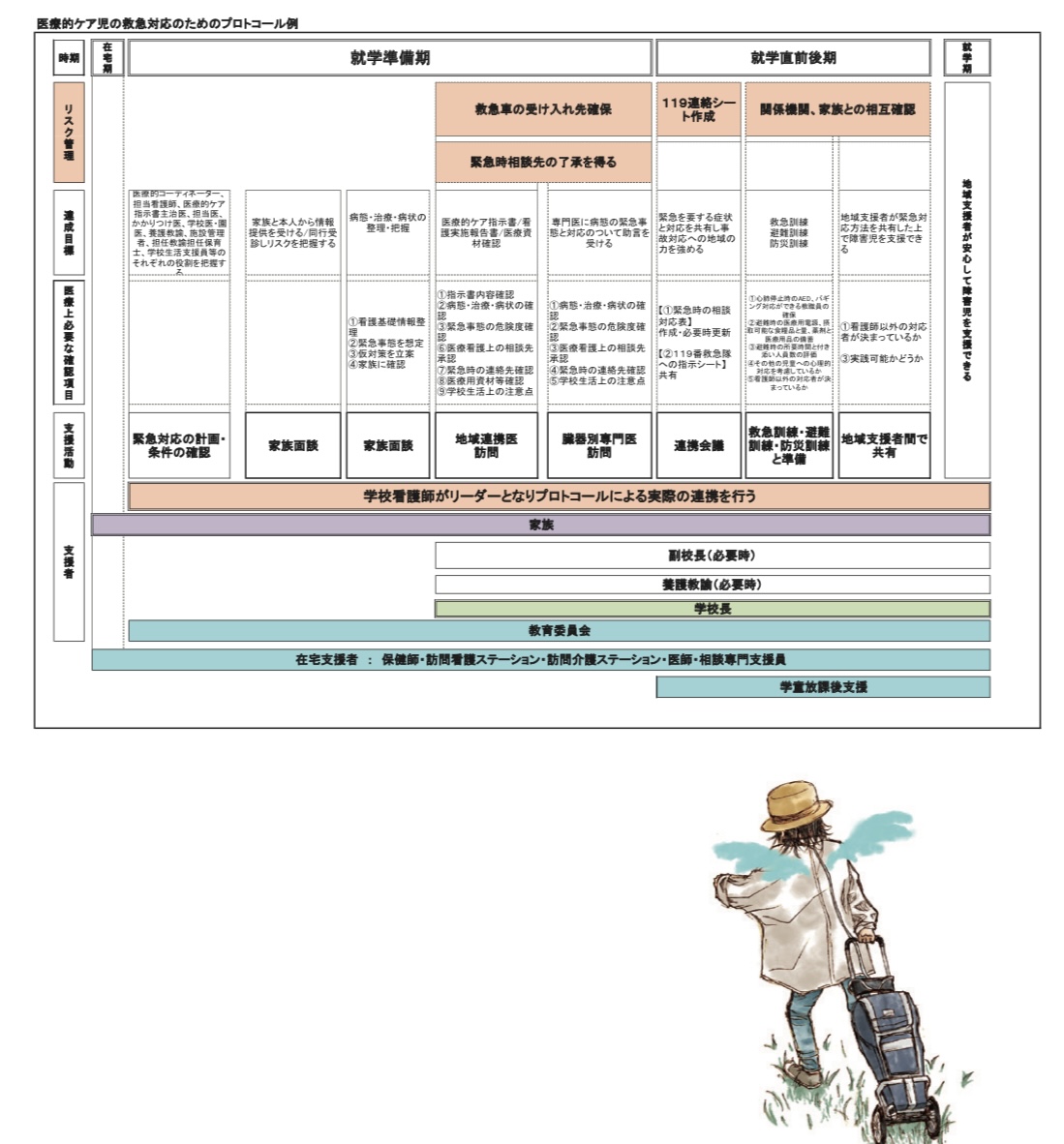
【入学までの支援】
①就学先との情報共有
医療的ケア児が、区立学校に就学希望の場合は、入学にあたり心配な事や配慮について、就学支援シートを活用して情報提供します。
学校生活の困難さを軽減するための調整や対応について、予め情報提供を行うことで、医療的ケア(たんの吸引、経管栄養、導尿)の提供に必要な環境調整や、合理的な配慮を行います。
②入学先の決定
教育委員会は、子どもの成長や発達に応じた就学先を検討したうえで、子どもの可能性を最大限伸ばせると考えられる学びの場を保護者へ提案します。保護者の方の意見を尊重し、最終的には教育委員会が決定します。
保護者の希望に基づき、特別支援学校、特別支援学級の学習体験を10月に実施します。特別支援学校への就学を希望される方は東京都の相談に引き継ぎます。提案と保護者のご希望が異なる場合は相談を継続し、就学先の決定のため保護者、学校、教育委員会との合意形成を図っています。
③保護者と就学相談担当者、医療的ケア児コーディネーターの面談
前年11~12月、医療的ケア児コーディネーター資格をもつ看護師と就学相談担当者が保護者面談を実施します。訪問や家庭訪問または主治医の外来受診の同行など1~2時間程度面談を行います。事前に質問リストを送って、書面上で確認の上準備をしてもらうケースもあります。
就学相談担当がヒアリングした情報を、医療的ケア児コーディネーターが看護師の視点で改めて確認を行います。
上記の基礎情報の具体的な項目は①診断名②これまでの経過③担当機関と担当概要、治療方針④最近の症状、合併症⑤療育、保育状況⑥医療的ケアの実施状況、今後の希望⑦これまでの他のお子さんと保護者への説明内容⑧本人が納得できる病気のストーリー⑨学校で配慮して欲しいこと、学校行事等です。
外来受診同行等で主治医に以下の項目について指導を受けたり、依頼をします。①学校から緊急搬送する際の受け入れ先の協力依頼②緊急対応の指導の承諾③予測、回避すべき症状や合併症とその危険性の程度についての情報提供④最新の検査結果と今後の治療方針についての情報提供書作成の依頼
④主治医への指示書依頼、医療機関との情報共有
教育委員会は、保護者の同意を経て、主治医から医療的ケア指示書を取得します(医療機関への発行依頼と文書料の支払いは保護者に対応を依頼)。
必要に応じて、医療的ケア児コーディネーター資格のある看護師が同行をして主治医や専門医等の多職種から情報収集や指導を受けます、看護師から訪問看護事業所にコンタクトをとり、看護師間の連携を図ることもあります。